五十肩の痛みで悩んでいませんか?つらい痛みを何とかしたいけど、どの湿布を選べばいいのかわからない…という方は必見です。このページでは、五十肩の痛みの原因とメカニズムを解説した上で、市販薬で手に入る様々な湿布の種類と効果を徹底比較!ロキソニンテープやモーラステープなど、よく知られている湿布の特徴や効果的な使い方、選び方まで詳しく説明します。炎症を抑えるタイプ、痛みを和らげるタイプ、血行を促進するタイプなど、それぞれの湿布の特徴を理解することで、あなたの痛みに最適な湿布を見つけられます。また、湿布使用時の注意点や、湿布以外の五十肩対策、病院で処方される湿布との違いについても解説。五十肩の痛みを効果的に緩和し、快適な日常生活を取り戻すための情報が満載です。この記事を読めば、あなたにぴったりの湿布がきっと見つかるはずです。
1. 五十肩の痛みの原因とメカニズム
五十肩は、中高年に多く発症する肩関節の痛みや運動制限を伴う疾患です。正式名称は肩関節周囲炎といい、その名の通り肩関節周囲の組織に炎症が起こることが主な原因と考えられています。加齢とともに肩関節周囲の組織が老化し、柔軟性や弾力性が低下することで炎症が起きやすくなるとされています。また、肩関節をあまり動かさない生活習慣や、過度な運動による負担、姿勢の悪さなども五十肩の発症リスクを高める要因となります。五十肩の痛みは、日常生活に支障をきたすだけでなく、精神的なストレスにもつながるため、適切なケアと治療が重要です。
1.1 五十肩とは?
五十肩とは、肩関節周囲炎の俗称で、40~50歳代に多く発症することからこの名前が付けられています。しかし、実際には30代や60代以降でも発症する可能性があり、特定の年齢層に限定される病気ではありません。肩関節とその周囲の筋肉、腱、靭帯、関節包などに炎症が起こり、痛みや運動制限を引き起こします。五十肩は自然に治癒するケースも多いですが、適切な治療を行わないと痛みが慢性化したり、肩関節の可動域が狭くなって日常生活に支障をきたす場合もあります。早期に適切な対処をすることが重要です。
1.2 五十肩の痛みの特徴
五十肩の痛みは、安静時にも痛みを感じることが特徴です。特に夜間や朝方に痛みが強くなる傾向があり、睡眠を妨げることもあります。また、腕を特定の方向に動かすと激痛が走る場合があり、髪を洗ったり、服を着脱したりといった日常動作が困難になることもあります。痛みの程度や範囲は個人差があり、鈍痛から鋭い痛みまで様々です。さらに、肩の痛みだけでなく、腕や手、背中にまで痛みが広がることもあります。これらの症状は、炎症の進行とともに変化していくため、痛みの特徴を把握しておくことが大切です。
1.3 なぜ五十肩は痛むのか?
五十肩の痛みは、肩関節周囲の組織に炎症が起こることで発生します。炎症の原因ははっきりと解明されていませんが、加齢による組織の老化や、肩関節の使い過ぎ、外傷などが関係していると考えられています。炎症が起こると、炎症物質であるプロスタグランジンが産生されます。このプロスタグランジンが、痛みを感じる神経を刺激することで、肩に痛みを生じさせます。また、炎症によって肩関節周囲の組織が腫れ上がり、神経を圧迫することで痛みが増強される場合もあります。
| 炎症の段階 | 症状 | 期間 |
|---|---|---|
| 急性期 | 安静時痛、夜間痛、運動時痛が強く、肩関節の動きが制限される | 数週間~数ヶ月 |
| 慢性期 | 痛みは軽減するが、肩関節の動きが制限された状態が続く | 数ヶ月~1年 |
| 回復期 | 痛みと運動制限が徐々に改善していく | 数ヶ月~1年 |
五十肩は、これらの急性期、慢性期、回復期を経て自然に治癒していくことが多いですが、個人差が大きく、数年以上症状が続く場合もあります。それぞれの段階で適切な治療を行うことで、痛みの軽減や治癒期間の短縮を図ることが可能です。
2. 湿布の種類と効果
五十肩の痛みを和らげるために、様々な種類の湿布が市販されています。それぞれに含まれる成分や効果が異なるため、ご自身の症状に合った湿布を選ぶことが重要です。ここでは、五十肩によく用いられる湿布の種類と効果について詳しく解説します。
2.1 炎症を抑える湿布(非ステロイド性抗炎症薬:NSAIDs)
非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)は、炎症を抑え、痛みや腫れを軽減する効果があります。五十肩の急性期、つまり炎症が強い時期に特に有効です。ただし、胃腸障害などの副作用が現れる可能性もあるため、使用上の注意をよく読んで正しく使用しましょう。
2.1.1 ロキソニンテープ
ロキソプロフェンナトリウム水和物を主成分とするロキソニンテープは、強力な鎮痛消炎効果で知られています。比較的早く効果が現れるため、急性の痛みや炎症を抑えるのに適しています。貼付剤以外にも、内服薬、ゲル剤、スプレー剤など様々な剤形があります。
2.1.2 モーラステープ
ケトプロフェンを主成分とするモーラステープは、炎症を抑える効果に加え、血行を促進する作用も持ち合わせています。持続時間が長く、痛みが長引く場合に適しています。貼付剤以外にも、ゲル剤があります。
2.1.3 ボルタレンテープ
ジクロフェナクナトリウムを主成分とするボルタレンテープは、炎症や痛みを抑える効果があります。即効性があり、痛みが強い場合に効果的です。貼付剤以外にも、ゲル剤、スプレー剤、坐剤など様々な剤形があります。また、テープ剤には、テープとゲル剤の中間のような「パップ剤」と呼ばれる種類もあります。
2.2 痛みを和らげる湿布(鎮痛消炎成分配合)
痛みを和らげることを目的とした湿布には、様々な鎮痛消炎成分が配合されています。NSAIDsとは異なる成分で、副作用が少ない傾向にあるため、NSAIDsの使用を避けたい方にもおすすめです。
2.2.1 フェルビナク配合湿布
フェルビナクを主成分とする湿布は、優れた鎮痛消炎作用を発揮します。肩や腰などの関節痛、筋肉痛に効果的です。貼付剤以外にも、ゲル剤があります。
2.2.2 インドメタシン配合湿布
インドメタシンを主成分とする湿布は、痛みや炎症を抑える効果があります。慢性的な痛みにも効果を発揮します。貼付剤以外にも、ゲル剤、坐剤など様々な剤形があります。
2.3 血行を促進する湿布
血行を促進する湿布は、患部の血流を良くすることで、痛みやこわばりを和らげる効果があります。五十肩の慢性期、つまり痛みが長引いている場合に適しています。温感タイプのものが多く、冷えによる痛みにも効果的です。
2.3.1 トウガラシエキス配合湿布
トウガラシエキスを主成分とする湿布は、温感作用により血行を促進し、筋肉の緊張を和らげます。肩こりや腰痛にも効果的です。
2.3.2 サリチル酸メチル配合湿布
サリチル酸メチルを主成分とする湿布は、皮膚から吸収されて患部の血行を促進し、痛みを和らげます。筋肉痛や関節痛に広く用いられています。
| 湿布の種類 | 主成分 | 効果 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| ロキソニンテープ | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | 鎮痛、消炎 | 比較的早く効果が現れる |
| モーラステープ | ケトプロフェン | 鎮痛、消炎、血行促進 | 持続時間が長い |
| ボルタレンテープ | ジクロフェナクナトリウム | 鎮痛、消炎 | 即効性がある |
| フェルビナク配合湿布 | フェルビナク | 鎮痛、消炎 | 副作用が少ない傾向 |
| インドメタシン配合湿布 | インドメタシン | 鎮痛、消炎 | 慢性的な痛みにも効果的 |
| トウガラシエキス配合湿布 | トウガラシエキス | 血行促進、温感作用 | 肩こりや腰痛にも効果的 |
| サリチル酸メチル配合湿布 | サリチル酸メチル | 血行促進、鎮痛 | 筋肉痛や関節痛に広く使用 |
それぞれの湿布の効果や特徴を理解し、ご自身の症状に合った湿布を選びましょう。また、湿布を使用する際には、使用上の注意をよく読み、用法・用量を守って正しく使用することが大切です。症状が改善しない場合は、使用を中止し、専門家にご相談ください。
3. 五十肩に効く湿布の選び方
五十肩の痛みを効果的に和らげるためには、湿布の種類を正しく理解し、自分の症状に合ったものを選ぶことが重要です。痛みの種類、炎症の程度、肌への負担など、様々な要素を考慮しながら最適な湿布を選びましょう。
3.1 痛みの種類に合わせた湿布選び
五十肩の痛みは、炎症によるもの、筋肉の緊張によるもの、神経の圧迫によるものなど、様々な原因が考えられます。痛みの種類によって適切な湿布も異なってきます。
| 痛みの種類 | おすすめの湿布 | 湿布の成分・効果 |
|---|---|---|
| 鋭い痛み、炎症が強い | ロキソニンテープ、ボルタレンテープ | 非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)が炎症を抑え、痛みを緩和します。 |
| 鈍い痛み、筋肉の凝り | モーラステープ、フェルビナク配合湿布 | 鎮痛消炎成分が筋肉の炎症や痛みを和らげます。血行促進効果のある湿布との併用も有効です。 |
| ジンジンする痛み、神経痛 | インドメタシン配合湿布 | インドメタシンは、神経痛にも効果があるとされています。 |
3.2 炎症の程度に合わせた湿布選び
炎症が強い場合は、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)を含む湿布が効果的です。ロキソニンテープやボルタレンテープなどが代表的です。炎症が軽度の場合や、痛みが慢性化している場合は、モーラステープやフェルビナク配合湿布など、鎮痛消炎成分を含む湿布が適しています。
3.2.1 炎症が強い場合
ロキソニンテープやボルタレンテープなどの非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)を含む湿布を選びましょう。これらの湿布は、炎症の原因物質であるプロスタグランジンの生成を抑えることで、炎症と痛みを効果的に緩和します。
3.2.2 炎症が軽度~中等度の場合
モーラステープやフェルビナク配合湿布などが適しています。これらの湿布は、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)ほど強力な抗炎症作用はありませんが、比較的穏やかに痛みを和らげます。また、血行促進作用のあるトウガラシエキス配合湿布やサリチル酸メチル配合湿布を併用することで、より効果的に痛みを緩和できる場合があります。
3.3 肌への負担を考慮した湿布選び
湿布は、長時間貼っていると肌がかぶれたり、赤くなったりすることがあります。特に敏感肌の方は、湿布の成分によって肌トラブルを起こしやすいので注意が必要です。肌が弱い方は、パスタイムFX7などの、微香性で肌に優しい湿布を選ぶと良いでしょう。また、同じ場所に長時間貼り続けず、定期的に貼り替えることも大切です。湿布を貼る前に、皮膚を清潔にしておくことも肌トラブルの予防に繋がります。
もし湿布でかぶれてしまった場合は、すぐに使用を中止し、患部を清潔にして冷やしましょう。症状が改善しない場合は、専門家に相談してください。
4. 湿布の効果的な使い方
五十肩の痛みを効果的に和らげるためには、湿布の正しい使い方を知ることが重要です。貼る場所、頻度、注意点などを理解し、適切に使用することで、より高い効果が期待できます。また、湿布以外の五十肩対策も併用することで、よりスムーズな回復を目指しましょう。
4.1 湿布の貼る位置と頻度
湿布は、痛みが強く感じられる部分に直接貼るのが基本です。五十肩の場合、肩関節周囲の筋肉や腱に炎症が生じているため、肩の前側、横側、後ろ側など、痛む場所に合わせて貼る位置を調整しましょう。痛みの原因となっている筋肉や腱を特定し、ピンポイントで貼ることで、より効果的に痛みを和らげることができます。痛みの出ている部分だけでなく、周辺の筋肉にも貼ることで、より広い範囲に効果が期待できます。
湿布の使用頻度は、製品によって異なります。必ず使用上の注意をよく読み、指示された用法・用量を守りましょう。一般的には、1日1~2回、患部に貼るのが適切です。貼り替えの際は、前の湿布を剥がしてから、新しい湿布を貼りましょう。同じ場所に長時間貼り続けると、皮膚への負担が大きくなる可能性があります。
| 湿布の種類 | 貼る位置の目安 | 頻度 |
|---|---|---|
| ロキソニンテープ | 肩関節周囲の痛みのある部分 | 1日2回 |
| モーラステープ | 肩関節周囲の痛みのある部分、炎症が強い部分 | 1日1~2回 |
| フェルビナク配合湿布 | 肩関節周囲の痛みのある部分 | 1日1~2回 |
| トウガラシエキス配合湿布 | 肩や首のこり、血行不良の部分 | 1日1~数回 |
4.2 湿布使用時の注意点
湿布を使用する際には、いくつかの注意点があります。まず、湿布を貼った部分に直射日光が当たらないように注意しましょう。日光に当たると、皮膚が炎症を起こしやすくなります。また、入浴時には湿布を剥がすようにしましょう。湿布を貼ったまま入浴すると、薬剤が皮膚から吸収されやすくなり、副作用のリスクが高まる可能性があります。湿布を剥がした後は、皮膚をよく洗い流し、清潔に保ちましょう。
湿布でかぶれやすい方は、特に注意が必要です。かぶれが生じた場合は、すぐに使用を中止し、患部を清潔に保ちましょう。症状が改善しない場合は、専門家に相談することをおすすめします。また、同じ場所に長時間貼り続けると、皮膚への負担が大きくなるため、定期的に貼り替えるようにしましょう。
4.2.1 湿布と併用したいケア
- 温熱療法:温めることで血行が促進され、痛みが和らぐ効果が期待できます。蒸しタオルや温湿布などを利用しましょう。
- ストレッチ:肩関節の可動域を広げるためのストレッチは、五十肩の改善に効果的です。無理のない範囲で行いましょう。
- 安静:痛みがあるときは、無理に肩を動かさないようにし、安静を保つことが大切です。痛みが強い場合は、サポーターなどで肩を固定することも有効です。
4.3 湿布以外の五十肩対策
五十肩の痛みを和らげるためには、湿布以外にもさまざまな対策があります。温熱療法は、血行を促進し、筋肉の緊張を和らげる効果があります。蒸しタオルやカイロなどで肩を温めると、痛みが軽減されることがあります。また、ストレッチも効果的です。肩関節の可動域を広げるストレッチを毎日行うことで、五十肩の症状を改善することができます。ただし、痛みがある場合は無理に行わず、専門家の指導を受けるようにしましょう。
日常生活での注意点も重要です。重いものを持ち上げたり、無理な姿勢を続けたりすることは、五十肩の症状を悪化させる可能性があります。できるだけ肩に負担をかけないように注意し、必要に応じてサポーターなどを活用しましょう。また、十分な睡眠をとることも、体の回復を促すために重要です。
痛みが強い場合や、症状が改善しない場合は、我慢せずに専門家に相談しましょう。適切な治療を受けることで、早期の回復が期待できます。自己判断で治療を中断せず、専門家の指示に従うことが大切です。
5. ロキソニンテープとモーラステープの比較
五十肩の痛みを和らげるために使用する湿布として、ロキソニンテープとモーラステープはどちらも広く知られています。しかし、それぞれの特徴や効果には違いがあります。自分に合った湿布を選ぶために、それぞれの違いを理解しておきましょう。
5.1 ロキソニンテープの特徴と効果
ロキソニンテープの主成分はロキソプロフェンナトリウム水和物です。これは非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)と呼ばれる種類の薬で、炎症や痛みを引き起こすプロスタグランジンの生成を抑えることで、炎症と痛みを鎮める効果があります。即効性が高いのも特徴で、急性の痛みや炎症に効果を発揮します。貼付剤タイプなので、患部に直接作用し、効果が持続します。
ロキソニンテープには、様々なサイズや形状が用意されています。肩などの広い範囲に貼る大きなサイズや、関節など動きのある部分に貼りやすい伸縮性のあるタイプなど、症状や部位に合わせて選ぶことができます。
5.1.1 ロキソニンテープの種類
- ロキソニンSテープ
- ロキソニンSプラスター
- ロキソニンEXテープ
5.2 モーラステープの特徴と効果
モーラステープの主成分はケトプロフェンです。こちらも非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)の一種で、ロキソニンテープと同様に炎症と痛みを鎮める効果があります。ロキソニンテープに比べると効果の発現はやや緩やかですが、持続時間が長いという特徴があります。そのため、慢性的な痛みや、夜間も続く痛みなどに適しています。
モーラステープも様々な種類が販売されており、患部の状態や好みに合わせて選択できます。温感タイプは、血行を促進し、筋肉の緊張を和らげる効果も期待できます。
5.2.1 モーラステープの種類
- モーラステープ
- モーラスパップXR
- モーラスワン
5.3 どちらの湿布が自分に合っているか
ロキソニンテープとモーラステープ、どちらの湿布が自分に合っているかは、痛みの種類や程度、持続時間などによって異なります。
| 項目 | ロキソニンテープ | モーラステープ |
|---|---|---|
| 主成分 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | ケトプロフェン |
| 効果の発現 | 速い | やや遅い |
| 効果の持続時間 | やや短い | 長い |
| 適した痛み | 急性の痛み、強い痛み | 慢性的な痛み、夜間も続く痛み |
急な痛みや強い痛みにはロキソニンテープ、慢性的な痛みや夜間も続く痛みにはモーラステープが適していると言えます。ただし、これはあくまでも一般的な目安です。湿布の使用については、使用上の注意をよく読み、適切に使用してください。また、症状が改善しない場合は、専門家への相談も検討しましょう。
6. 市販薬と病院で処方される湿布の違い
五十肩の痛みを和らげるために、薬局で購入できる市販薬の湿布と、病院で処方される湿布があります。それぞれにどのような違いがあるのでしょうか。成分、効き目、費用などの面から比較してみましょう。
6.1 成分の違い
市販薬の湿布と病院で処方される湿布では、配合されている成分の種類や濃度が異なります。
| 種類 | 主な成分 | 特徴 |
|---|---|---|
| 市販薬の湿布 | サリチル酸メチル、フェルビナク、インドメタシン、l-メントールなど | 比較的作用が穏やかで、副作用が少ない成分が配合されています。痛みの種類や程度に合わせて様々な成分の湿布が販売されているので、自分に合ったものを選ぶことができます。 |
| 病院で処方される湿布 | ジクロフェナクナトリウム、ケトプロフェン、フェンタニルなど | 市販薬よりも強力な鎮痛消炎作用を持つ成分が配合されている場合があります。痛みが強い場合や、市販薬で効果が不十分な場合に処方されることが多いです。 |
6.2 効き目の違い
市販薬の湿布は、比較的軽度の痛みや炎症に効果があります。痛みが強い場合や慢性的な痛みには、病院で処方される湿布の方が効果が高いことが多いです。また、同じ成分でも、病院で処方される湿布の方が高濃度で配合されている場合があり、より高い効果が期待できることがあります。
6.3 費用の違い
市販薬の湿布は、全額自己負担で購入します。病院で処方される湿布は、健康保険が適用されるため、自己負担額は市販薬よりも安くなることが多いです。ただし、初診料や再診料などの診察費用がかかります。
6.4 副作用のリスク
湿布は外用薬ですが、皮膚のかぶれ、発疹、かゆみなどの副作用が起こる可能性があります。特に、病院で処方される湿布は、成分が強力なため、副作用のリスクも高くなる傾向があります。使用前に、医師または薬剤師に相談し、適切な使用方法を守ることが大切です。
6.5 使い分けのポイント
軽度の痛みや炎症には、市販薬の湿布を試してみましょう。痛みが強い場合や、市販薬で効果が不十分な場合は、病院を受診し、適切な湿布を処方してもらいましょう。また、持病がある方や、妊娠中の方、授乳中の方は、使用前に医師または薬剤師に相談するようにしてください。
7. 五十肩の湿布に関するよくある質問
五十肩の痛みを和らげるために湿布を使用する際、様々な疑問が生じるかと思います。ここでは、よくある質問とその回答をまとめました。
7.1 Q. 湿布はどのくらいの期間使い続けてもいいですか?
湿布の使用期間は、痛みの程度や湿布の種類によって異なります。一般的には、同じ種類の湿布を5~7日間連続で使用しても問題ないとされています。しかし、痛みが改善しない場合や悪化した場合、もしくは7日間使用しても効果がない場合は、使用を中止し、専門家へ相談しましょう。また、慢性的な痛みに対しては、湿布の長期使用は推奨されません。痛みの原因を特定し、適切な治療を受けることが重要です。
7.2 Q. 複数の種類の湿布を同時に使用しても大丈夫ですか?
複数の種類の湿布を同時に使用することは、一般的には推奨されません。それぞれの湿布に含まれる成分が相互作用を起こし、副作用のリスクが高まる可能性があります。また、どの湿布が効果を発揮しているのかが分かりにくくなり、適切な治療の妨げになる可能性も。どうしても複数の湿布を使用したい場合は、必ず専門家に相談しましょう。異なる部位に異なる種類の湿布を使用する場合でも注意が必要です。
7.3 Q. 湿布でかぶれてしまった場合はどうすればいいですか?
湿布でかぶれてしまった場合は、すぐに使用を中止し、患部を清潔に保ちましょう。石鹸などは使用せず、ぬるま湯で優しく洗い流すのがおすすめです。かぶれの症状が軽い場合は、数日で自然に治まることが多いです。しかし、赤みやかゆみが強い場合、水ぶくれができている場合、発熱を伴う場合などは、速やかに専門家を受診しましょう。自己判断で市販薬を使用することは避け、適切な治療を受けてください。
7.4 Q. 湿布を貼る部位に汗をかいている場合はどうすればいいですか?
湿布を貼る部位に汗をかいている場合は、汗をしっかりと拭き取ってから湿布を貼りましょう。汗が残っていると、湿布がはがれやすくなるだけでなく、かぶれの原因にもなります。清潔なタオルやガーゼなどで、患部を優しく丁寧に拭き、乾燥させてから湿布を貼ってください。
7.5 Q. 冷湿布と温湿布、五十肩にはどちらが良いですか?
五十肩の症状によって、適した湿布の種類が異なります。
| 症状 | おすすめの湿布 | 理由 |
|---|---|---|
| 急性期(炎症が強く、熱感がある) | 冷湿布 | 炎症を抑え、痛みを和らげる |
| 慢性期(炎症が落ち着き、こわばりが強い) | 温湿布 | 血行を促進し、筋肉の緊張を和らげる |
7.6 Q. 妊娠中や授乳中に湿布を使用しても大丈夫ですか?
妊娠中や授乳中に湿布を使用する場合は、必ず専門家に相談してください。湿布に含まれる成分によっては、胎児や乳児に影響を与える可能性があります。自己判断で使用せず、専門家の指示に従いましょう。
7.7 Q. 貼り薬タイプの湿布と塗り薬タイプの湿布、どちらが五十肩に効果的ですか?
貼り薬タイプの湿布は、患部に直接薬剤を届けることができるため、持続的な効果が期待できます。一方、塗り薬タイプの湿布は、広範囲に塗布することができ、マッサージ効果も期待できます。どちらが効果的かは、痛みの部位や症状、個人の好みによって異なります。自分に合った方を選びましょう。
7.8 Q. 湿布以外の五十肩対策はありますか?
湿布以外にも、五十肩対策として有効な方法があります。温熱療法やストレッチ、運動療法などがあります。自分に合った方法を選び、継続して行うことが重要です。痛みが強い場合は無理せず安静にし、専門家に相談しましょう。
8. まとめ
五十肩の痛みを和らげるには、適切な湿布選びが重要です。この記事では、五十肩の原因とメカニズム、そして様々な種類の湿布の効果と選び方について解説しました。非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)であるロキソニンテープやモーラステープ、ボルタレンテープは炎症を抑える効果が高く、痛みの初期段階に有効です。フェルビナクやインドメタシン配合の湿布も鎮痛効果が期待できます。一方、トウガラシエキスやサリチル酸メチル配合の湿布は血行を促進し、慢性的な痛みに効果的です。
湿布を選ぶ際には、痛みの種類や炎症の程度、肌への負担を考慮することが大切です。また、湿布の効果的な使い方や注意点についても理解しておく必要があります。湿布はあくまで対症療法であり、痛みが長引く場合は医療機関への受診が推奨されます。五十肩の根本的な改善には、医師の指導のもと、適切な治療とリハビリテーションを行うことが重要です。この記事が、つらい五十肩の痛みを和らげるための湿布選びの一助となれば幸いです。
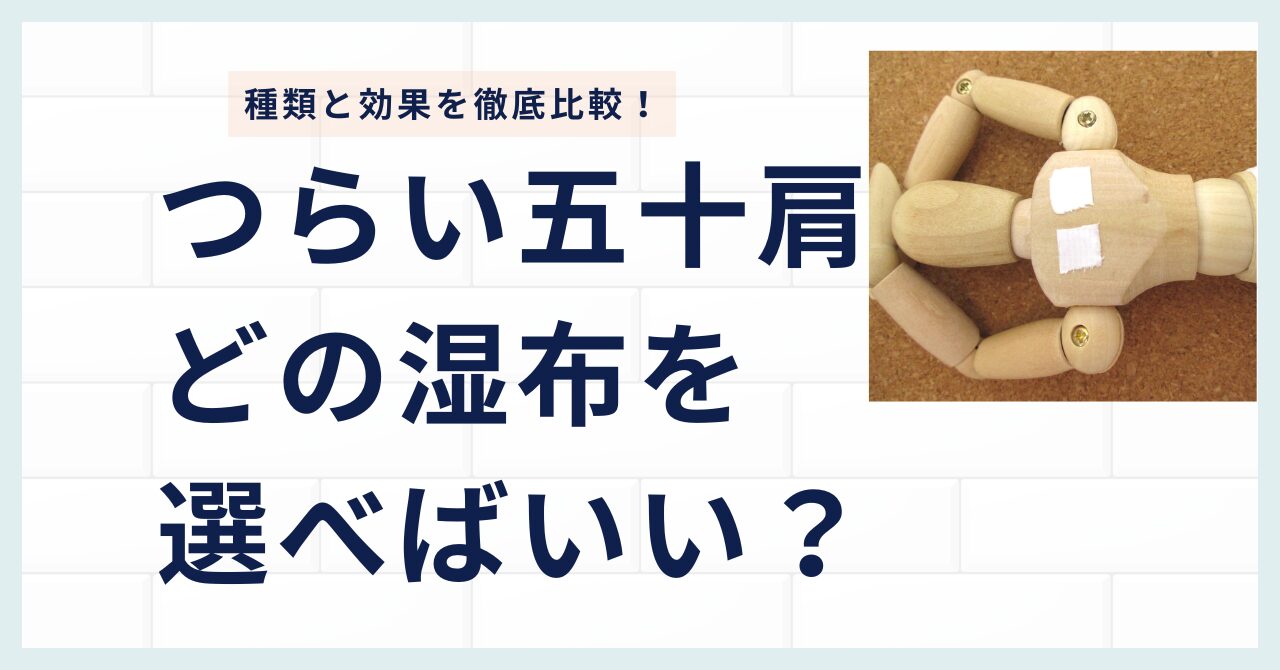

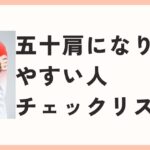
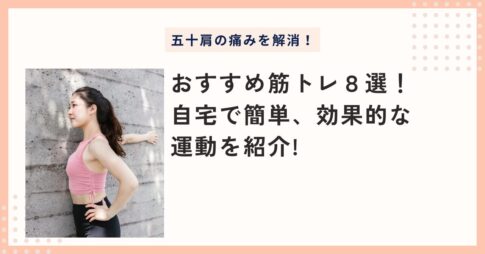

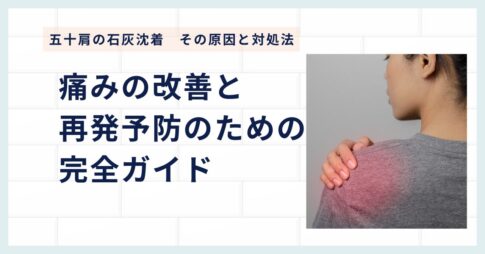
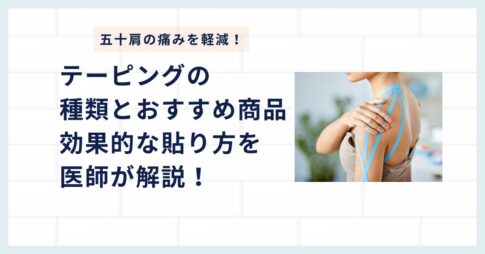
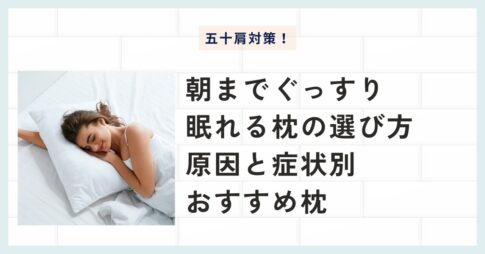
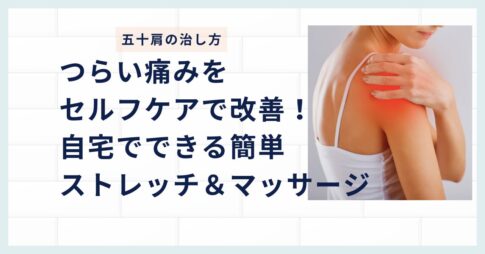
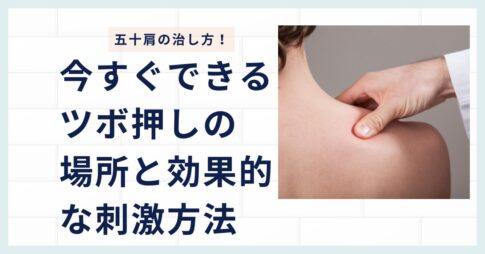
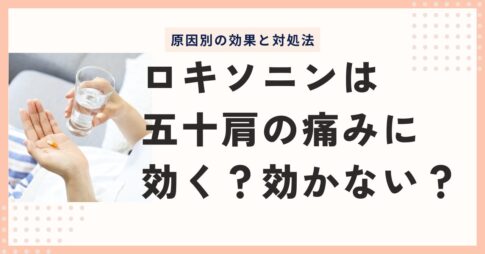
コメントを残す