つらい五十肩の痛み。適切な運動で症状を改善し、快適な日常生活を取り戻したいと思いませんか? このページでは、五十肩の原因や症状を分かりやすく解説した上で、自宅で簡単にできる効果的な運動方法を具体的にご紹介します。肩甲骨を動かす準備運動から、痛みが出ない範囲で行うストレッチ、クールダウンまで、一連の流れを丁寧に解説。さらに、運動の効果を高めるためのポイントや注意点、日常生活での工夫についても詳しく説明します。五十肩の痛みを軽減し、肩の動きをスムーズにするための実践的な情報が満載です。この記事を読めば、五十肩の改善に向けて、今日から何をすべきか、具体的な行動が見えてきます。
1. 五十肩とは?
五十肩は、正式には肩関節周囲炎と呼ばれ、肩関節とその周辺組織に炎症や痛み、運動制限が生じる疾患です。40代から50代に多く発症することから、五十肩という俗称で広く知られています。ただし、50歳以外でも発症する可能性があり、30代や60代でも見られることがあります。加齢とともに発症リスクは高まりますが、加齢だけが原因ではなく、様々な要因が複雑に絡み合って発症すると考えられています。
1.1 五十肩の症状
五十肩の症状は、大きく分けて3つの時期に分けられます。
| 時期 | 症状 | 期間 |
|---|---|---|
| 急性期 | 安静時にもズキズキとした強い痛みがあり、夜間痛で睡眠が妨げられることもあります。肩を動かすと激痛が走り、腕を上げたり、後ろに回したりすることが困難になります。 | 数週間~数ヶ月 |
| 慢性期 | 強い痛みは軽減しますが、肩関節の動きが制限された状態が続きます。腕を特定の方向に動かすと痛みが出たり、肩が突っ張るような感覚があります。日常生活動作にも支障が出ることがあります。 | 数ヶ月~半年 |
| 回復期 | 徐々に痛みや運動制限が改善していきます。肩の可動域が広がり、日常生活動作もスムーズに行えるようになります。ただし、完全に元の状態に戻るまでには時間がかかる場合もあります。 | 数ヶ月~1年以上 |
これらの時期は明確に区別されるわけではなく、症状の経過には個人差があります。また、適切な治療を行わないと、慢性的な痛みが残ったり、肩関節の可動域が制限されたままになる可能性もあります。
1.2 五十肩の原因
五十肩の明確な原因は解明されていませんが、肩関節周囲の組織の炎症や、肩関節を構成する骨、腱、靭帯、関節包などの老化が関係していると考えられています。また、以下の要因も発症リスクを高める可能性があります。
- 肩関節の使い過ぎ
- 肩関節の外傷
- 長時間のデスクワーク
- 猫背などの不良姿勢
- 運動不足
- 糖尿病
- 甲状腺疾患
これらの要因が単独で五十肩を引き起こすわけではなく、複数の要因が組み合わさって発症すると考えられています。したがって、日常生活の中で肩への負担を軽減し、適切な運動を行うことが五十肩の予防につながります。
2. 五十肩運動の効果
五十肩に悩まされている方にとって、適切な運動は症状改善の鍵となります。五十肩運動は、肩関節の可動域を広げ、痛みを軽減するだけでなく、日常生活の質向上にも繋がります。この章では、五十肩運動によって得られる効果とその重要性について詳しく解説します。
2.1 五十肩運動で得られる効果とは
五十肩運動には、様々な効果が期待できます。大きく分けて、以下の3つの効果が挙げられます。
| 効果 | 詳細 |
|---|---|
| 肩関節の可動域拡大 | 五十肩になると、肩関節周囲の筋肉や組織が硬くなり、腕を上げたり回したりすることが困難になります。運動によってこれらの組織が柔軟性を取り戻し、可動域が改善されます。 |
| 痛みの軽減 | 肩の痛みは、炎症や筋肉の緊張によって引き起こされます。適切な運動は、血行を促進し、筋肉の緊張を和らげ、炎症を抑える効果があり、結果として痛みの軽減に繋がります。 |
| 日常生活動作の改善 | 五十肩によって制限されていた、着替えや洗髪、高い場所の物を取るといった日常生活動作がスムーズに行えるようになります。生活の質の向上に大きく貢献します。 |
これらの効果に加えて、五十肩運動は精神的な面にも良い影響を与えます。運動によって身体を動かすことで、気分がリフレッシュし、ストレス軽減にも繋がります。また、運動を通して得られる達成感は、五十肩克服へのモチベーション維持にも役立ちます。
2.2 運動療法が重要な理由
五十肩の治療において、運動療法は非常に重要な役割を担っています。安静にするだけでは、肩関節周囲の筋肉や組織が硬くなってしまい、可動域の制限や痛みが慢性化する可能性があります。適切な運動療法を行うことで、これらの悪循環を断ち切り、早期回復を目指せます。また、運動療法は、他の治療法(温熱療法や電気療法など)の効果を高める上でも重要です。運動によって血行が促進され、温熱療法や電気療法の効果がより浸透しやすくなります。
五十肩の症状や進行度合いは人それぞれです。そのため、運動療法を行う際は、自身の状態に合わせた適切な運動を選択することが重要です。無理な運動は症状を悪化させる可能性があるので、痛みや違和感を感じた場合はすぐに中止し、専門家に相談しましょう。
3. 自宅でできる効果的な五十肩運動
五十肩の痛みを和らげ、肩関節の動きを改善するためには、自宅でできる運動療法が非常に効果的です。無理のない範囲で、毎日継続して行うことが大切です。ご紹介する運動は、五十肩の症状に合わせて適宜選択・組み合わせ、ご自身のペースで行ってください。
3.1 準備運動:肩甲骨を動かす体操
肩甲骨周りの筋肉をほぐし、血行を促進することで、よりスムーズに五十肩運動を行えるようになります。肩甲骨を意識的に動かすことを心がけましょう。
3.1.1 肩甲骨回し
両腕を肩の高さに上げて肘を曲げ、手のひらを前に向けます。肩甲骨を意識しながら、肘で円を描くように前後にゆっくりと回します。前回し10回、後ろ回し10回を目安に行いましょう。
3.1.2 肩甲骨寄せ
両腕を体の横に伸ばし、手のひらを上に向けます。胸を張ったまま、両肩甲骨を背骨の中心に寄せるように意識し、ゆっくりと5秒間キープします。これを5~10回繰り返します。肩甲骨が動いていることを感じながら行いましょう。
3.2 五十肩運動:痛みが出ない範囲で行うストレッチ
痛みを感じない範囲で、無理なく行うことが重要です。痛みが強い場合は運動を中止し、様子を見てください。以下の運動は、五十肩の主な症状である、肩の痛みや可動域制限の改善に効果的です。
3.2.1 振り子運動
体を前かがみにし、痛みのある腕を下に垂らします。リラックスした状態で、腕を前後に、左右に、そして円を描くように振り子のように動かします。それぞれの動きを10回ずつ行いましょう。腕の重さを利用して、肩関節に負担をかけないように注意してください。
3.2.2 タオルを使ったストレッチ
タオルの両端を持ち、背中に回し、痛みのある腕側の手を少し下にします。反対側の手でタオルを上に引き上げ、痛みのある腕を無理なく伸ばします。この姿勢を20秒間キープし、3~5回繰り返します。肩甲骨がストレッチされているのを感じながら行いましょう。タオルの長さを調整することで、ストレッチの強度を変えることができます。
3.2.3 壁を使ったストレッチ
壁の前に立ち、痛みのある側の腕を壁につけ、指先を壁に沿って上に動かしていきます。痛みを感じない範囲で、できるだけ高く上げていきましょう。この姿勢を20秒間キープし、3~5回繰り返します。肩関節の可動域を広げる効果が期待できます。
3.3 クールダウン:肩周りの筋肉をリラックスさせる
運動後は、肩周りの筋肉をリラックスさせることが大切です。温めたタオルや蒸しタオルなどで肩を温めたり、優しくマッサージすることで、血行を促進し、筋肉の緊張を和らげることができます。5~10分程度行いましょう。
以下の表に、準備運動、五十肩運動、クールダウンをまとめました。
| 運動の種類 | 運動内容 | 回数/時間 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 準備運動:肩甲骨回し | 両腕を肩の高さに上げて肘を曲げ、手のひらを前に向け、肘で円を描くように前後に回す | 前回し10回、後ろ回し10回 | 肩甲骨を意識的に動かす |
| 準備運動:肩甲骨寄せ | 両腕を体の横に伸ばし、手のひらを上に向け、両肩甲骨を背骨の中心に寄せる | 5秒キープ×5~10回 | 肩甲骨が動いていることを感じながら行う |
| 五十肩運動:振り子運動 | 体を前かがみにし、腕を下に垂らし、前後に、左右に、円を描くように動かす | 各方向10回ずつ | リラックスした状態で行う |
| 五十肩運動:タオルを使ったストレッチ | タオルの両端を持ち、背中に回し、痛みのある腕側の手を少し下に。反対側の手でタオルを上に引き上げ、痛みのある腕を伸ばす | 20秒キープ×3~5回 | タオルの長さを調整して強度を変える |
| 五十肩運動:壁を使ったストレッチ | 壁の前に立ち、痛みのある側の腕を壁につけ、指先を壁に沿って上に動かす | 20秒キープ×3~5回 | 痛みを感じない範囲で行う |
| クールダウン | 温めたタオルや蒸しタオルなどで肩を温めたり、優しくマッサージする | 5~10分程度 | 血行を促進し、筋肉の緊張を和らげる |
これらの運動は、五十肩の症状改善に効果的ですが、すべての人に当てはまるわけではありません。ご自身の症状に合わせて、適切な運動を選択することが重要です。また、運動中に強い痛みを感じた場合は、すぐに運動を中止し、専門家にご相談ください。
4. 五十肩運動の効果を高めるためのポイント
五十肩運動の効果を最大限に引き出すためには、いくつかのポイントを押さえることが重要です。適切な頻度や時間、痛みとの付き合い方、そして正しい呼吸法を意識することで、より効果的に五十肩の改善を目指せます。
4.1 適切な頻度と時間
五十肩運動は、毎日行うことが理想的です。ただし、痛みがある場合は、無理せず休むことも大切です。 1回の運動時間は、10~15分程度を目安に行いましょう。短時間でも毎日続けることで、肩関節の柔軟性を維持し、可動域の改善に繋がります。
| 運動頻度 | 運動時間 | ポイント |
|---|---|---|
| 毎日 | 10~15分 | 継続することが重要 |
| 痛みがある場合 | 休止 | 無理は禁物 |
4.2 痛みとの付き合い方
五十肩運動を行う際に、痛みは必ずしも悪いものではありません。適度な痛みは、運動効果の指標となる場合もあります。 しかし、激しい痛みや、運動後に痛みが強くなる場合は、運動を中止し、安静にする必要があります。痛みの程度に合わせて運動の強度や時間を調整することが、効果を高める鍵となります。
4.2.1 痛みのレベル分けと対応
| 痛みのレベル | 対応 |
|---|---|
| 軽い痛み(我慢できる程度) | 運動を継続。ただし、無理はしない。 |
| 中程度の痛み(少し辛い) | 運動を中断し、様子を見る。痛みが引かない場合は、運動量を減らすか、中止する。 |
| 強い痛み(我慢できない) | 直ちに運動を中止し、安静にする。 |
4.3 呼吸法の重要性
五十肩運動を行う際には、深い呼吸を意識することが重要です。 呼吸を止めずに、ゆっくりと息を吸いながら腕を上げ、息を吐きながら腕を下ろすようにします。深い呼吸をすることで、肩周りの筋肉がリラックスし、運動効果が高まります。また、血行促進効果も期待できます。 腹式呼吸を意識することで、よりリラックス効果を高めることができます。
4.3.1 効果的な呼吸法
- 鼻から息を吸い、口から息を吐く
- 腹式呼吸を意識する
- 運動のリズムに合わせて呼吸する
これらのポイントを踏まえ、ご自身の状態に合わせた五十肩運動を実践することで、より効果的に症状の改善を目指しましょう。痛みや違和感を感じた場合は、自己判断せずに専門家に相談することが大切です。
5. 五十肩運動の注意点
五十肩の運動療法は、正しく行えば効果的な改善策となりますが、誤った方法や無理な実施は症状を悪化させる可能性があります。五十肩運動を行う際の注意点について詳しく解説します。
5.1 無理な運動は禁物
五十肩の痛みは個人差が大きく、同じ運動でも痛みの感じ方が異なります。痛みを我慢して無理に運動を続けると、炎症が悪化し、痛みがさらに強くなる可能性があります。「少し痛いけど我慢できる」程度の痛みであれば問題ありませんが、強い痛みを感じる場合はすぐに運動を中止してください。痛みが強い時は、安静にすることが大切です。
5.2 専門家との相談
五十肩の症状や進行度は人それぞれです。自己判断で運動を行うのではなく、専門家に相談し、自身の状態に合った適切な運動方法を指導してもらうことが重要です。専門家は、あなたの症状に合わせて、適切な運動の種類、強度、頻度などをアドバイスしてくれます。また、運動療法以外の治療法についても相談できます。
5.3 適切な運動方法の確認
五十肩運動は、正しいフォームで行うことが重要です。間違ったフォームで運動を行うと、効果が得られないばかりか、他の部位を痛めてしまう可能性もあります。専門家から指導を受けた際には、運動方法をしっかりと理解し、正しいフォームを身につけるようにしましょう。また、動画サイトなどで運動方法を確認する場合は、信頼できる情報源を選びましょう。
5.4 運動の種類と注意点
| 運動の種類 | 注意点 |
|---|---|
| 振り子運動 | 身体を前かがみにしすぎない。腕の力を抜いて、重力に任せて腕を振る。 |
| タオルを使ったストレッチ | タオルを持つ手の位置を調整し、無理なく肩甲骨を動かす。痛みを感じたらすぐに中止する。 |
| 壁を使ったストレッチ | 壁に手をつけたまま、無理に腕を上げない。肩甲骨を意識して、ゆっくりと腕を動かす。 |
| 肩甲骨回し | 肩甲骨を意識して大きく回す。肩をすくめないように注意する。 |
| 肩甲骨寄せ | 背筋を伸ばし、胸を張った状態で肩甲骨を寄せる。無理に力を入れすぎない。 |
5.5 運動中の違和感
運動中に痛み以外の違和感を感じた場合も、すぐに運動を中止し、専門家に相談しましょう。違和感には、しびれ、だるさ、熱感などがあります。これらの症状は、神経や血管の圧迫などが原因で起こる可能性があり、放置すると症状が悪化することがあります。自己判断で対処せず、専門家の指示に従うことが大切です。
5.6 運動環境
運動を行う際は、適切な環境で行うことも重要です。室温が低すぎると筋肉が硬くなり、ケガのリスクが高まります。冬場は暖房器具などで室温を上げ、夏場は冷房で冷やしすぎないように注意しましょう。また、滑りにくい服装や靴を着用し、周囲に危険な物がないか確認してから運動を始めましょう。
6. 五十肩運動以外の治療法
五十肩の痛みや可動域制限の改善には、運動療法が有効ですが、痛みが強い場合や運動療法だけでは十分な効果が得られない場合、他の治療法を組み合わせることがあります。それぞれの治療法の特徴を理解し、ご自身の症状に合った方法を選択することが大切です。
6.1 薬物療法
五十肩の痛みを抑えるためには、薬物療法が用いられることがあります。主に使用される薬には、次のようなものがあります。
6.1.1 消炎鎮痛剤
炎症を抑え、痛みを和らげる効果があります。内服薬だけでなく、湿布薬や塗り薬などの外用薬も使用されます。
6.1.2 非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)
炎症や痛みを抑える効果が高い薬です。ロキソニンやボルタレンなどが代表的な薬です。
6.2 注射療法
五十肩の痛みが強い場合や、薬物療法で効果が不十分な場合、注射療法が用いられることがあります。代表的な注射療法には、次のようなものがあります。
6.2.1 関節内注射
ヒアルロン酸を関節内に注射することで、関節の動きを滑らかにし、痛みを軽減します。
6.2.2 ステロイド注射
炎症を抑える効果が非常に高いステロイド薬を、肩関節周囲に注射します。痛みが強い場合に有効ですが、副作用のリスクもあるため、慎重に判断する必要があります。
6.2.3 神経ブロック注射
痛みの原因となっている神経に局所麻酔薬を注射することで、痛みを遮断する方法です。痛みが強い場合に一時的な痛みの緩和が期待できます。
6.3 理学療法
理学療法士による専門的な指導のもと、様々な物理療法や運動療法を行います。五十肩の症状に合わせて、適切なプログラムを作成し、痛みの軽減や可動域の改善を目指します。主な理学療法には、次のようなものがあります。
| 種類 | 内容 | 効果 |
|---|---|---|
| 温熱療法 | ホットパックや赤外線などを用いて肩関節周囲を温める | 血行を促進し、筋肉の緊張を和らげる |
| 電気療法 | 低周波や干渉波などの電気を用いて、痛みを軽減する | 痛みの緩和、筋肉の収縮・弛緩の促進 |
| 牽引療法 | 肩関節を引っ張ることで、関節の動きを改善する | 関節可動域の改善 |
| 運動療法 | 理学療法士の指導のもと、肩関節周囲の筋肉を強化する運動を行う | 筋力強化、関節可動域の改善 |
これらの治療法は、単独で行われることもありますが、組み合わせて行うことでより効果的な治療となる場合もあります。 どの治療法が適切かは、症状の程度や個々の状態によって異なります。治療を受ける際は、専門家とよく相談し、ご自身に合った治療法を選択することが重要です。
7. 日常生活での注意点
五十肩の改善には、運動療法だけでなく日常生活での注意点も重要です。適切な姿勢や冷え対策、質の高い睡眠を心がけることで、より効果的に五十肩の症状を和らげ、再発を予防することができます。
7.1 姿勢
猫背や前かがみの姿勢は、肩甲骨の動きを制限し、肩関節への負担を増大させます。正しい姿勢を意識することで、肩周りの筋肉の緊張を緩和し、血行を促進できます。具体的には、顎を引いて背筋を伸ばし、肩の力を抜くことを意識しましょう。デスクワークが多い方は、椅子に深く腰掛け、モニターの位置を目の高さに合わせるなど、作業環境を整えることも大切です。
7.1.1 正しい姿勢のポイント
| 部位 | ポイント |
|---|---|
| 頭 | 顎を引いて、耳の穴と肩を一直線に |
| 肩 | 力を抜いてリラックス |
| 背中 | 伸ばして、肩甲骨を寄せるイメージ |
| 腰 | 反りすぎず、自然なS字カーブを保つ |
7.2 冷え対策
冷えは血行不良を招き、肩関節の周りの筋肉を硬くし、痛みを悪化させる可能性があります。特に冬場は、肩や首を冷やさないように注意しましょう。マフラーやストール、カイロなどを活用して保温するのも効果的です。また、シャワーだけでなく、湯船に浸かって体を温めることで、血行促進効果が期待できます。入浴剤を使用するのも良いでしょう。ぬるめのお湯にゆっくりと浸かることで、リラックス効果も得られます。
7.2.1 冷え対策の具体的な方法
- 温かい服装を心がける:重ね着をして体温調節をしましょう。
- 温かい飲み物を飲む:生姜湯やハーブティーなどがおすすめです。
- 適度な運動をする:ウォーキングなどの軽い運動で血行を促進しましょう。ただし、痛みがある場合は無理をしないでください。
- バランスの良い食事を摂る:体を温める効果のある根菜類などを積極的に摂取しましょう。
7.3 睡眠の質
質の高い睡眠は、体の回復を促し、五十肩の改善にも繋がります。睡眠不足は、自律神経のバランスを崩し、痛みを悪化させることがあるため、十分な睡眠時間を確保することが重要です。寝る前にカフェインを摂取するのは避け、リラックスできる環境を作ることを心がけましょう。アロマを焚いたり、ヒーリングミュージックを聴いたりするのも効果的です。また、寝具にもこだわり、自分に合った枕やマットレスを選ぶことで、より快適な睡眠を得ることができます。
7.3.1 睡眠の質を高めるためのヒント
- 規則正しい生活リズムを保つ:毎日同じ時間に寝起きすることで、体内時計が整います。
- 寝る前にリラックスする時間を作る:読書や軽いストレッチなどがおすすめです。
- 寝室の環境を整える:室温や照明を調整し、快適な空間を作りましょう。
- 睡眠時間を確保する:7時間程度の睡眠時間を目安にしましょう。
8. 五十肩運動に関するよくある質問
五十肩に関する運動療法について、よくある質問にお答えします。
8.1 運動中に痛みが出たらどうすればいいですか?
運動中に痛みが出た場合は、直ちに運動を中止してください。痛みを我慢して運動を続けると、症状が悪化することがあります。痛みが引かない場合は、安静にして様子を見ましょう。数日経っても痛みが続く場合は、専門家への相談も検討してください。
8.2 どのくらいの期間で効果が出ますか?
五十肩運動の効果が出るまでの期間は、症状の重さや個人差によって大きく異なります。一般的には、数週間から数ヶ月かけて徐々に効果が現れることが多いです。焦らず、毎日コツコツと続けることが大切です。また、効果を高めるためには、適切な頻度や時間、正しい方法で運動を行うことが重要です。痛みが強い時期は無理せず、痛みが軽減してきたら徐々に運動量を増やしていくようにしましょう。
8.3 五十肩は自然に治りますか?
五十肩は、自然に治る場合もありますが、適切な治療や運動を行わないと、痛みが長引いたり、肩関節の動きが悪くなることがあります。五十肩の症状が疑われる場合は、自己判断せずに専門家に相談し、適切な指導を受けることをお勧めします。
8.4 五十肩運動は毎日行うべきですか?
五十肩運動は、毎日行うことが理想ですが、痛みが強い場合は、無理に行う必要はありません。痛みの程度に合わせて、運動の頻度や強度を調整しましょう。毎日行うのが難しい場合は、1日おきや週に数回でも構いません。少しでも肩を動かすことで、血行が促進され、症状の改善に繋がります。
8.5 どんな時に専門家に相談するべきですか?
以下の症状がある場合は、専門家に相談することをお勧めします。
| 症状 | 説明 |
|---|---|
| 夜間痛がひどい | 夜に痛みが強くなり、睡眠に支障が出る場合。 |
| 腕が上がらない、後ろに回せない | 日常生活に支障が出るほど、肩の可動域が制限されている場合。 |
| 痛みが数週間以上続く | 適切なケアを行っても、痛みが改善しない場合。 |
| しびれや脱力感がある | 肩の痛みだけでなく、腕や手にしびれや脱力感がある場合。 |
| 肩以外の部位にも痛みがある | 首や背中など、肩以外の部位にも痛みがある場合。 |
8.6 効果的な五十肩運動の種類は?
五十肩運動には様々な種類がありますが、代表的なものとして、振り子運動、タオルを使ったストレッチ、壁を使ったストレッチなどがあります。これらの運動は、自宅で簡単に行うことができ、肩関節の可動域を広げる効果が期待できます。自分に合った運動を選び、無理なく続けることが大切です。具体的な運動方法については、専門家に相談するか、信頼できる情報源を参考にしましょう。
8.7 五十肩運動以外にできることはありますか?
五十肩の改善には、運動療法だけでなく、日常生活での注意点も重要です。例えば、正しい姿勢を保つ、肩を冷やさない、質の良い睡眠をとるなど、日常生活の中でできる工夫を心がけることで、五十肩の症状を軽減することができます。また、温熱療法や冷却療法なども効果的です。自分に合った方法を見つけることが大切です。
五十肩の症状や治療法には個人差があります。疑問や不安があれば、専門家に相談し、適切なアドバイスを受けるようにしましょう。
9. まとめ
五十肩の痛みや可動域制限の改善には、適切な運動療法が非常に重要です。この記事では、自宅でできる効果的な五十肩運動をご紹介しました。肩甲骨を動かす準備運動から始め、痛みが出ない範囲で振り子運動やタオル、壁を使ったストレッチを行い、クールダウンまで行うことで、肩関節の柔軟性を取り戻し、痛みを軽減することができます。効果を高めるためには、適切な頻度と時間で運動を行い、痛みとの付き合い方や呼吸法にも気を配ることが大切です。無理な運動は避け、医師や理学療法士に相談しながら、自分に合った運動方法を見つけるようにしましょう。五十肩は自然治癒することもありますが、適切な治療と日常生活での注意点を守ることで、より早く改善し、再発予防にも繋がります。この記事で紹介した運動や注意点を実践し、快適な日常生活を取り戻しましょう。何かお困りごとがありましたら当院へお問い合わせください。
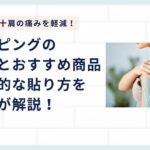
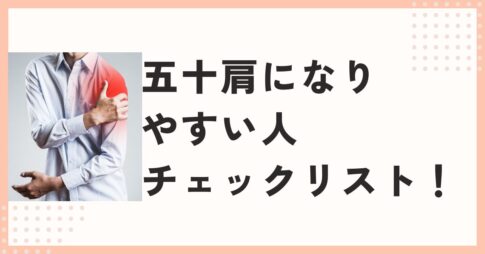

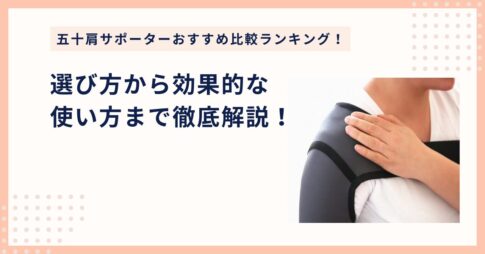
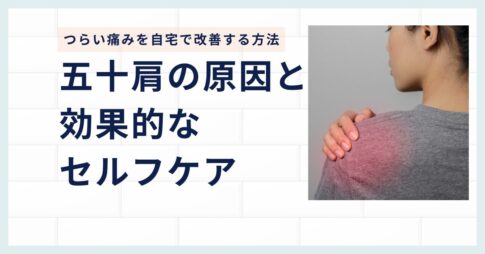
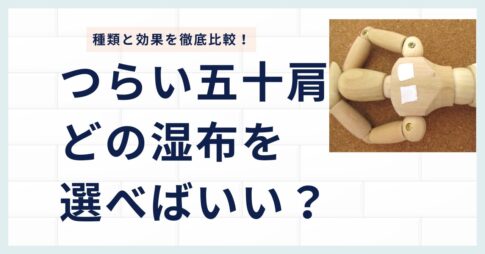
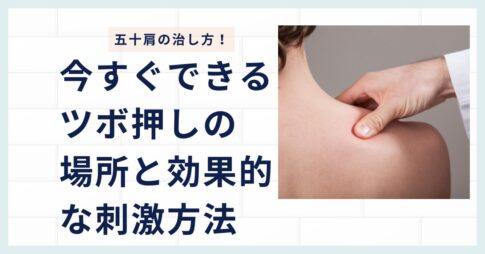
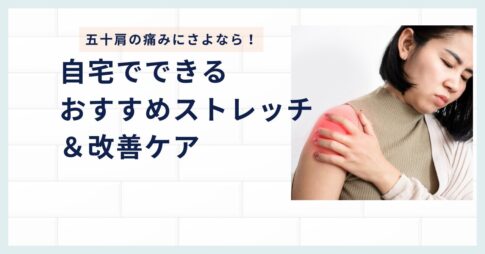
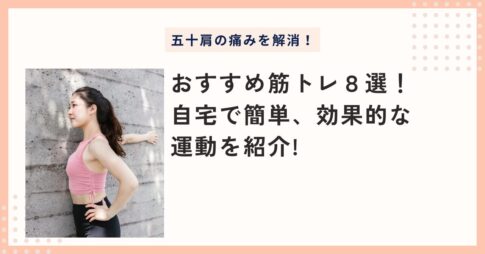
コメントを残す